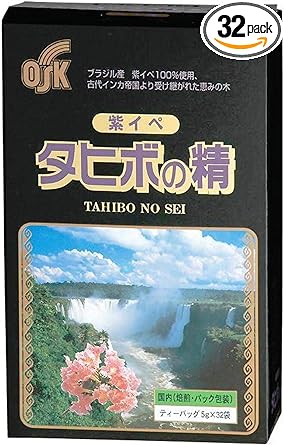ベートーヴェンとフリーメイソンの関係

初めに断っておきますが、私がこう言った記事を書く理由は過去の芸術、クラシック音楽を批判したいからではありません。
著者がどういった信条を持ち、創作していたかというところに焦点を当てて話が進んでいくのですが…極端な話、作者が悪魔的なものを意図せず作ったものでも、世の支配者たちが都合よくそれを悪の象徴として扱うこともあるでしょう。
ですので、ベートーヴェンはフリーメイソン!はい黒!悪魔的!地獄に堕ちたくないなら彼の作る曲は聞かない方がいいよ!…と安直にはいかないはずです。(多分)
ただ、悪魔崇拝者たちが支配する世の中でもてはやされるものは悪魔的な要素があると疑うことは間違ってないと思います。
最近だとPPAPですか。リンゴ。露骨すぎてもう…って感じです。しかも流行りだしたのがジャスティン・ビーバーのツイートに端を発してるとか。ジャスティン・ビーバーといえば完全にイルミナティー側です。
話がそれましたが、クラシックの話題に戻ります。
ショパン本人が気に入ってなくて、遺言の中で楽譜を燃やすようと言った程の『幻想即興曲』が世の中ではやたらと持ち上げられ、彼の代表曲のようにされているのが皮肉としか思えないのは私だけでしょうか。しかもop.66です。気味が悪いですよね。
死後に発表された曲と言ったらベートーヴェンにもありますよね。そう、『エリーゼのために』です。
この曲、世の中に出回っているのは本人が大幅に修正する前のスケッチ(楽曲のアイデアを想い浮かべ、譜面に下書きしたもの)だというのです。
驚くことに、そのスケッチには私達が知っている『エリーゼのために』とは明らかに異なる大掛かりな修正が書き加えられていて、ベートーウ゛ェンにとってこの曲が未完成作品だったということが窺えるのです。
出典 : 『エリーゼのために』2|たかちゃんのピアノ
ショパンと同じく、作者の意図しない形で世の中に出回っている典型ですね。しかもベートーヴェンの場合は曲として完成してないものですから、もし本人が生きていてこの状況を見たら怒っちゃうかもしれませんね。
世の中的にその人の代表曲とされている曲には何か意図を感じてしまいますよね。
ここでようやく本題に移ります。
ベートーヴェンが作曲した曲でひときわ持ち上げられているあの曲。毎年毎年、年末に大合唱されるあの曲。なんでわざわざあの曲を、しかも大人数で歌うんだろ、のあの曲。そう、交響曲第9番『第九』です。
この第九で最も有名なのは第4楽章で歌われる歓喜の歌でしょう。そしてこの歓喜の歌こそ、フリーメイソンの理念を詩にしたものを引用したものだったのです。
『歓喜の歌』(かんきのうた、喜びの歌、歓びの歌とも。独: An die Freude / アン・ディー・フロイデ、英: Ode to Joy)は、ベートーヴェンの交響曲第9番の第4楽章で歌われ、演奏される第一主題のこと。
歌詞は、シラーの詩作品「自由賛歌」(独: Ode An die Freiheit[1]、仏: Hymne à la liberté[2] 1785年)がフランス革命の直後ラ・マルセイエーズのメロディーでドイツの学生に歌われていた。そこで詩を書き直した「歓喜に寄せて」(An die Freude 1785年初稿、1803年一部改稿)にしたところ、これをベートーヴェンが歌詞として1822年 – 1824年に引用書き直したもの。ベートーヴェンは1792年にこの詩の初稿に出会い、感動して曲を付けようとしているが、実際に第9交響曲として1824年に完成した時には、1803年改稿版の詩を用いている。1785年のシラーの「自由」(Freiheit / フライハイト)の詩はフリーメイソンの理念を詩にしたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれた。
出典 :
歌詞の内容ですが、これがまたヒドイです。「汝が魔力は再び結び合わせる」「快楽は虫けらのような者にも与えられ 智天使ケルビムは神の前に立つ」「星空の上に神を求めよ」などなど…
「星空の上に神を求めよ」って…この歌詞で言う神とはバフォメッド(悪魔)のことですか?
出典 : 悪魔崇拝と星の関係 | 新・世界の裏
歓喜に寄せての歌詞はこちら。
「歓喜に寄せて」
おお友よ、このような旋律ではない!
もっと心地よいものを歌おうではないか
もっと喜びに満ち溢れるものを
(ベートーヴェン作詞)歓喜よ、神々の麗しき霊感よ
天上楽園の乙女よ
我々は火のように酔いしれて
崇高な汝(歓喜)の聖所に入る汝が魔力は再び結び合わせる
(1803年改稿)
時流が強く切り離したものを
すべての人々は兄弟となる
(1785年初稿:
時流の刀が切り離したものを
物乞いらは君主らの兄弟となる)
汝の柔らかな翼が留まる所でひとりの友の友となるという
大きな成功を勝ち取った者
心優しき妻を得た者は
彼の歓声に声を合わせよそうだ、地上にただ一人だけでも
心を分かち合う魂があると言える者も歓呼せよ
そしてそれがどうしてもできなかった者は
この輪から泣く泣く立ち去るがよいすべての存在は
自然の乳房から歓喜を飲み
すべての善人もすべての悪人も
薔薇の路をたどる自然は口づけと葡萄酒と
死の試練を受けた友を与えてくれた
快楽は虫けらのような者にも与えられ
智天使ケルビムは神の前に立つ神の壮麗な計画により
太陽が喜ばしく天空を駆け巡るように
兄弟よ、自らの道を進め
英雄のように喜ばしく勝利を目指せ抱き合おう、諸人(もろびと)よ!
この口づけを全世界に!
兄弟よ、この星空の上に
愛する父がおられるのだひざまずくか、諸人よ?
創造主を感じるか、世界よ
星空の上に神を求めよ
星の彼方に必ず神は住みたもう
出典 : 嘘八百のこの世界:第九は大工であり石工でありフリーメーソンそのものなのかもしれません。
ところで智天使ケルビムって何でしょう。引用元によると、ケルビムは堕天使ではないかという説明がなされています。つまり、サタン(悪魔)ということでしょう。
この言葉からすれば、サタンは守護天使ケルブ(ケルビム)のひとりであった、という意味に取れます。堕落前のサタンは、天使のひとりであり、しかも長のような存在であったのでしょう。
出典 : 嘘八百のこの世界:第九は大工であり石工でありフリーメーソンそのものなのかもしれません。
歓喜の歌が悪魔的な内容であることはもう疑いの余地がないようですね。他にもベートーヴェンが作曲した曲で、フリーメイソンを思わせる曲があります。交響曲第3番『英雄』です。
さて、そのフリーメイソンの思想の中にこそ人類の未来があると確信し、その思想に従い芸術的作品を創造しようとしたベートーヴェン。
特に耳の病で一時は絶望のどん底に落ちた彼にとってこの思想こそ、残された人生をかくも人間賛歌を歌い上げる歓喜・勝利に導いたとしています。
その一大転機となった曲があの「英雄」だということです。確かに多くの点で革新的・創造的なものを持つ傑作に異論はありません。
そこで、調べてみるとフリーメイソンの音楽的シンボルというものがあってその主なものは次のような事柄です。1.基本的な調性が「変ホ長調」であること
2.戸を叩くリズム(特に3)が明確に示されていること
3.儀式的な雰囲気を表す和声進行が見られること交響曲第3番「英雄」の調性が♭3つの変ホ長であること、第一楽章を3/4拍子にしたこと、さらに冒頭のザン!ザン!というテュッティの主和音が曲全体を支配する二本の柱となっていることなど、その条件を満たしています。
出典 :
ここまで来ると、ベートーヴェンもフリーメイソンの会員だったのか…と思えてきてしまうのですが、入信記録は残っていないようです。
音楽家ではハイドンやモーツァルトなどがフリーメーソンの会員であったことはよく知られているが、ベートーヴェンについては、その入信記録は見つかっていない。
だたベートーヴェンの場合、ボン時代はもとよりウィーンに出てからも、リヒノフスキーやブルンスヴィック、あるいはエルデーディ夫人やズメスカルなど、そのパトロンや友人のほとんどがメーソンであり、彼自身のアイデンティティーにメーソン的な思想基盤があったことは疑いない。それにもかかわらず入信しなかったとすれば、彼は思想信条は共有するが、いかなる集団の掟にも縛られたくないとする独特の自由精神の持主だったと見ることもできよう。そして1812年までは、唯一絶対の〈神〉とその他の多様な〈神々〉とは、彼の信仰心の中で混交しつつ共存していたのではなかったろうか。
出典 : ◆ベートーヴェンとフリーメーソンの関係、宗教観そして「神」~青木やよひ著『ベートーヴェンの生涯』よ – 音楽家ピアニスト瀬川玄「ひたすら音楽」
会員だったかどうかはともかく、歓喜に寄せてのような超悪魔的な内容の詩に感銘を受けるようですから、神様的には決して褒められた人じゃありません。音楽的な才能はあったんでしょうけど。